
- トップ
- わたしたちについて
- 連絡会員とは(事業者・法人向け)
- 応援サポーターとは(一般向け)
- リアルハブイベントとは
- イベント情報
- お知らせ・活動報告
- 連絡会員一覧
- お問い合わせ
- 利用規約
- プライバシーボリシー
〒561-0881
豊中市中桜塚2-25-12-205

〒561-0881
豊中市中桜塚2-25-12-205

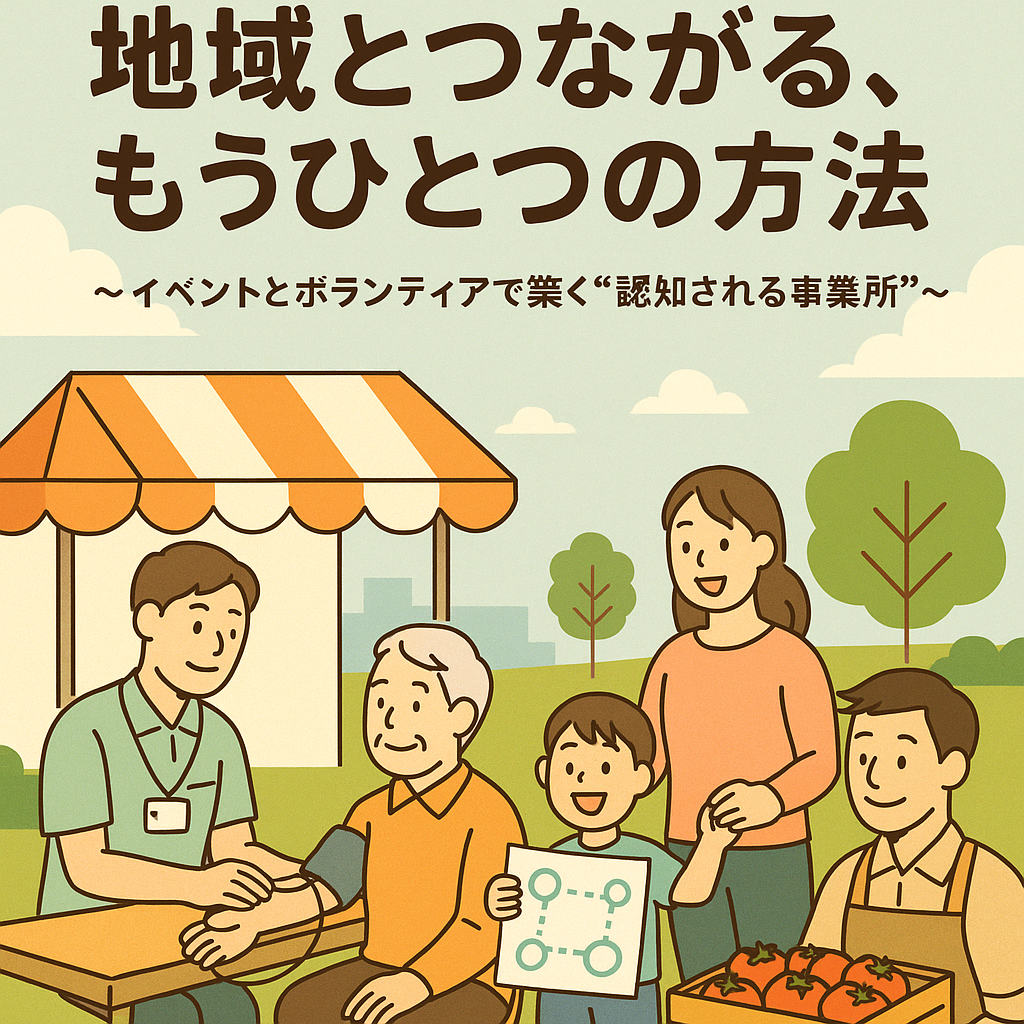
〜イベントとボランティアで築く“認知される事業所”〜
週末の午後、地域の公園で開催されたにぎやかなイベント会場。介護福祉の専門職が、子どもたちと一緒にスタンプラリーを運営したり、高齢者向けの健康測定ブースを開いていたり。スタッフと住民の笑顔が交わるその場には、“告知”や“宣伝”といった空気はなく、ただ「いっしょに楽しむ」場が広がっていました。
たとえば、豊中市内で開催されている「いきてゆくフェス」も、そうした“ひらかれた福祉の場”のひとつです。福祉事業所やボランティア団体、地域住民が協力して企画・運営を行い、子どもから高齢者まで、多様な人々が自然と集う仕組みがつくられています。ここに共通するのは、「まず楽しめること」が重視されている点です。
介護施設や事業所が「もっと地域に知ってほしい」と願うのは当然のことです。しかし、「施設見学会」「サービス説明会」だけでは、地域の方の足はなかなか向きません。
理由のひとつは、“関係ない世界”と思われていること。もうひとつは、参加する側にとっての「楽しさ」や「発見」が感じにくいことです。
情報発信の場ではなく、“地域との交差点”としてのイベント設計が求められています。
事業所側の「知ってほしい」と、地域側の「行ってみたい」の間には、温度差があります。
そのギャップを埋める工夫が、イベントやボランティア活動には不可欠です。
たとえば:
このような“誰にとっても楽しめる入口”を用意することで、参加者は「地域の中にある介護」を自然と受け止めることができます。
地域との接点づくりには、日常の延長線上にあるようなイベントや取り組みが有効です。以下のような形で、他地域でも成果が報告されています。
こうした取り組みを継続することで、施設名や職員の顔が地域で“見覚えのあるもの”になっていきます。
重要なのは、「参加してよかった」と思える体験が、信頼や記憶につながるという点です。単発ではなく、地域に根を張る継続性が力になります。
介護事業所が地域に開くとは、何かを“発信する”ことではなく、“一緒に過ごす場をつくる”こと。
その中で、事業所の役割や人となりが少しずつ伝わっていく。そんな関わり方が、今求められているのではないでしょうか。
地域イベントやボランティアは、認知度向上のための手段であると同時に、関係性を育てる場でもあります。
「誰にとっても魅力的な場づくり」を意識しながら、次の一歩を踏み出してみませんか。
