これまで、『地域包括ケアシステム』における介護保険事業者の役割や地域福祉の向上のために何をすべきかについて考察してきました。
地域包括ケアシステムを構築するためには、介護保険事業者は介護サービスの質の向上はもちろん、地域の自助活動や互助活動を支える姿勢が大切です。
しかし、現代の介護業界が直面している大きな課題が人材不足。この対策の一つとして「ワークシェアリング」が注目されています。そこで今回は、介護施設におけるワークシェアリングについて考えてみたいと思います。
2040年には「約272万人」の介護職員が必要!?
少子高齢化の進行に伴い、介護ニーズは増加しています。厚生労働省によると、2026年度の介護職員の必要数は約240万人。そして、1947年〜1949年の第1次ベビーブーム期に生まれた「団塊の世代」の子どもにあたる「団塊ジュニア世代」が65歳を迎えて高齢者人口がピークとなると予想されている2040年には約272万人の介護職員が必要とされています。
出典:第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について|厚生労働省
介護職員不足を防ぐ新しい働き方「ワークシェアリング」
このような中、介護職員をスムーズに確保し、介護サービスの質を維持するために注目されている新たな仕組みが「ワークシェアリング」です。
ワークシェアリングとは、特定の業務を複数の介護職員で分担し、それぞれが得意とする分野で働く仕組みです。この制度により、フルタイムで働けない職員でも短時間で特定の業務に携わることができ、介護施設側もシフトを柔軟に運用可能となります。例えば、入浴介助や食事介助を特定の事業所に登録したスタッフが担当し、必要な時だけ働くことができるのです。
ワークシェアリングのメリットとは?
- 特定の職員にかかる業務負担の軽減
介護現場における業務は多岐に渡ります。そんな中、特定の職員に多くの業務が集中してしまうと過労やストレスの原因となりうるでしょう。ワークシェアリングを導入することで業務が分散され、各職員の負担軽減が期待できます。
- 短期間でも活躍できる人材の増加
フルタイム勤務が難しい人材の雇用機会が広がります。例えば、育児や家族の介護などを理由に正社員という働き方を離れた人でも、ワークシェアリングを利用すれば短時間で新たに働き始めることができるのです。
- 柔軟にシフト調整をしやすくなる
急な病欠や予定外の欠員が発生した際に、その時間に空いている他の人材を確保し、業務に支障が出ることを防げます。これにより、安定した介護サービスの提供が可能です。
ワークシェアリングを導入する際のポイント
ワークシェアリングを成功させるためには、事前に現在の業務内容を明確化し、マニュアルを整備することが欠かせません。また、既存職員へ対して事前にワークシェアリングの目的や仕組みを説明し、短時間のスポット就労でも心地よく働けるような受け入れ体制を整えることも必要です。ワークシェアリングで就労してもらったスタッフから働く上でやりにくかった点はなかったかなどのフィードバックをもらい、その後の改善に繋げていくことも大切でしょう。
人材不足に対応しながら、より良い介護サービスの提供を
介護業界の人材不足解消に向けて「ワークシェアリング」は有効な手段となり得ます。介護保険事業者にとって、人材不足に対応しながらより良い介護サービスを提供していく姿勢は、今後ますます重要となっていくでしょう。
豊中市介護保険事業者連絡会としても、介護保険事業者同士の連携強化や自己啓発に努めながら介護人材不足に対応していく所存です。過去には、介護コンサルティングの方を講師に招き「スタッフが定着する仕組みづくり ~人材育成のヒント~」といった研修会を開催しました。研修会の学びやその活かし方などについてはこちらの記事で発信していますので、ぜひ参考にしてみてください。




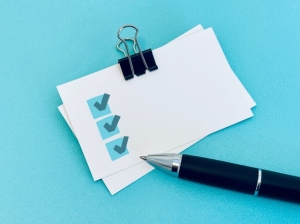





コメント